放課後等デイサービスは、発達に特性のある子どもたちが放課後や長期休暇中に安心して過ごせる「居場所」として注目を集めています。
特別支援教育や子どもとの関わりの経験をもつ元教員・教育関係者にとっても、第二のキャリアとして非常に相性の良い分野です。
ただし、放課後等デイサービスの開業には、法人設立や自治体からの指定申請など、明確な条件と準備が必要です。
「個人事業主では開業できない」など、行政のルールを理解しておかないと、思わぬところでつまずくこともあります。
この記事では、実際に開業した方々の事例や自治体の制度を参考に、開業までの流れ・指定のポイント・注意点をわかりやすく解説します。
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスとは、小学生から高校生までの発達障がいや知的障がいのある子どもを対象に、放課後や長期休暇中に支援を行う福祉サービスです。
子どもたちの生活能力の向上や社会参加の促進を目的としており、療育・学習支援・集団活動など幅広いプログラムが提供されています。
このサービスは「児童福祉法」に基づく事業であり、利用者は原則として自己負担1割、残りの9割は公費(自治体や国)によって賄われます。
そのため行政の指定を受けることが必須で、運営には厳格な基準と手続きが求められます。
開業には「法人格」が必須!個人事業主ではできません
放課後等デイサービスを開業するには、法人格を持っていることが絶対条件です。
個人事業主としての開業は認められていません。
認められている法人形態
| 区分 | 法人形態 |
|---|---|
| 営利法人 | 株式会社、合同会社 |
| 非営利法人 | 社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人 |
営利法人でも非営利法人でも開業は可能ですが、重要なのは法人としての運営体制と責任を果たせるかどうかです。
行政からの報酬(給付金)を受けて事業を行うため、透明性の高い会計処理や人員配置の管理が求められます。
法人設立と開業準備の進め方
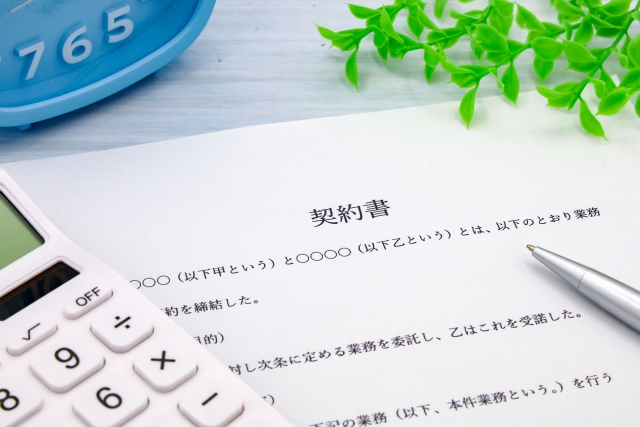
放課後等デイサービスを始めるには、まず法人設立 → 指定申請という二段階の手続きが必要です。
行政との調整や申請書類の準備には時間がかかるため、計画的に進めましょう。
① 法人設立の準備
開業地が決まったら、法人を立ち上げます。
「株式会社」または「合同会社」での設立が一般的で、流れは次のとおりです。
- 定款の作成
- 登記申請(法務局)
- 法人口座の開設
- 事業目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」を明記
設立には一定の資本金が必要ですが、最近では10万円程度から設立可能です。
ただし、自治体によっては「財務的安定性」を重視するため、資本金300万円程度を目安にする方もいます。
② 開業資金と融資相談
物件の確保・改修費・備品購入・人件費など、初期費用は数百万円規模になる場合があります。
そのため、日本政策金融公庫や地元金融機関の創業融資制度を利用するのが一般的です。
また、商工会議所や自治体の創業支援窓口を活用すると、無料で事業計画や融資相談を受けられます。
実際に多くの開業者が、退職前から商工会議所の相談を重ねて、有利な利率で融資を受けて法人を設立しています。
退職後に一気に動くのではなく、勤務中のうちから少しずつ準備することが成功のカギです。
自治体の「指定申請」が必要
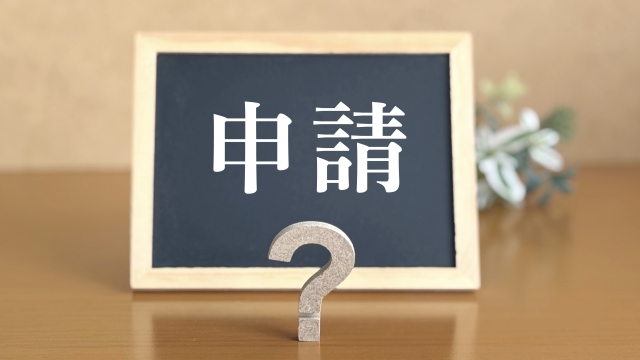
法人を設立しても、すぐに開業できるわけではありません。
放課後等デイサービスは「指定障害児通所支援事業」として、自治体(市町村または都道府県)からの指定を受ける必要があります。
指定申請の流れ
- 事前協議: 開業予定地の自治体へ相談し、事業計画や図面を確認してもらう。
- 必要書類の準備: 人員配置表、運営規程、資金計画などを作成。
- 申請書類の提出: 自治体の指定窓口に提出。
- 審査・現地確認: 書類審査と現地確認。
- 指定通知の交付: 基準を満たしていれば指定が下りる。
※自治体によっては、開業の約2か月前までに申請が必要です。
指定を受けるための基準
人員基準
| 職種 | 必要人数 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1名以上 | 事業全体の統括 |
| 児童発達支援管理責任者 | 1名以上 | 管理者と兼務可 |
| 児童指導員・保育士等 | 児童10名につき2名 | 資格者が必要 |
教員免許を持つ方は「児童指導員」として配置できるため、資格職の人は開業時に有利です。
設備基準
- 利用者1人当たりの面積:2.47㎡以上
- 安全・衛生面を確保した設備
- トイレ・避難経路などの確保
運営規程
- 非常災害時の対応
- 衛生管理
- 個人情報保護 など
開業時の注意点と落とし穴
放課後等デイサービスの指定基準は、自治体によって細部が異なります。
隣の市ではOKでも、自分の地域ではNGというケースもあるため、必ず開業予定地の指定権者に確認しましょう。
また、建物に関しては建築基準法・消防法・労働基準法など他の法令にも適合する必要があります。
特に「用途変更(住宅→福祉施設)」の手続きが必要になることが多いため、行政との事前調整が欠かせません。
指定後も、運営指導や5年ごとの更新があります。報酬請求の誤り(過誤請求)があると、返金が求められる場合もあります。
不安がある場合は、行政書士や社会福祉士など専門家に相談すると安心です。
まとめ|綿密な準備と信頼関係が成功のカギ

放課後等デイサービスの開業には、
- 法人の設立
- 指定申請
- 設備基準の整備
- 人員配置の確保
といった複数のハードルがありますが、綿密な準備と自治体との信頼関係づくりができれば、安定した運営は十分に実現可能です。
教員として培った経験や子どもへの理解は、放課後等デイサービスの現場でも大きな力になります。
子どもの成長を支えるという原点を大切に、一歩ずつ準備を重ねていけば、地域に愛される事業を築くことができるでしょう。
教育現場での経験を次のステージで活かし、社会に貢献できる新しいキャリアの形として歩み出す——。
それが、放課後等デイサービスの開業という選択です。
この記事が、あなたの新しい一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
🌱 教育に関わり続けたい方は、こちらも参考にどうぞ:
👉 スクールサポートスタッフ(SSS)の仕事内容・給料・働き方とは?
👉 〖子育て中の教員へ〗退職を現実にするための5つの準備




