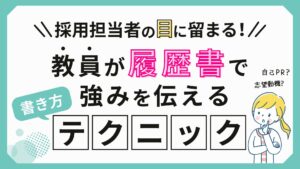はじめに
「教員の仕事は安定している」「子どもに関わる仕事はやりがいがある」──そんなイメージがあって教職を選んだ。私もそうでした。だけど、授業準備・部活動・保護者対応…気づけば朝から夜まで教員業務に追われ、子育ても自分の時間もほとんど取れない日々が続いていました。
40代に差し掛かったとき、こんな思いが私の中で強くなりました:
「このままでいいのかな」
「教員としてだけでなく、自分の人生も大切にしたい」
こういう悩みを抱えている教員の方、多いのではないでしょうか。この記事は、私が教員から一般企業に転職してから体験した“苦労したこと”“戸惑ったこと”、そしてそこから学んだことを正直に書いたものです。今転職を考えているあなたが、少しでも「未来はきっとこう変わるかもしれない」と思えるヒントになればうれしいです。
転職で気づいたこと:私のリアルな5つのギャップ
以下は、私が教員から一般企業で働き始めてから、毎日感じたギャップです。同じような悩みを持っている方に「こういう壁もあるんだ」と知ってほしいし、「でも超えられるよ」という気持ちも込めています。
ギャップ①:言葉遣いやマナーの細かい違いが思った以上に大きい
教員時代は「子どもに伝わるように」「柔らかく話す」ということが自然だったけれど、企業では正式な敬語、報連相のタイミング、電話の応対、メールの書き方など、求められる形式が違っていました。
例えば、以前は会議の場で親しい立場の先生に対して「うん、そうだね」と言っていたこともありました。でも新しい職場では、「はい、その通りです」「承知しました」のように、きちんとした応答が求められ、初めのうちはそれだけで緊張しました。
また、「リスケ」「アポ」など企業の省略語や英語混じりの言葉も多くて、聞き慣れないものがたくさんありました。説明されて初めて「ああ、そういう意味だったのか」と理解することが何度もあり、ノートを取りながら学んでいきました。
こういう細かい部分がわからないと、「デキない人」に見られてしまう不安が常にありました。でも、段々と慣れてくるものです。最初から完璧を目指すより、わからないことを素直に聞く姿勢が、自分を守ることにもつながります。
ギャップ②:評価の基準が“人の成長”より“数字と成果”

教員の仕事では、生徒たちができるようになる瞬間、保護者からの感謝、クラスの雰囲気が良くなるなど、目に見えにくい“成長”が報われる瞬間が多かったです。
でも企業では、成果が数値で表されることがすごく多い。「売上」「契約数」「達成率」など具体的な数字。それが目標であり、数字が足りないと評価が下がる。
私も営業職で転職したので、毎月の数字が自分の立ち位置を決めてしまうことに戸惑いもありました。「なぜ生徒のために頑張るのが評価されないのか」と思ったこともありました。
ただ、この経験を重ねるうちに、「数字は自分を励ます指標にもなる」という気持ちが芽生えました。目標が明確だから、逆に自分がどこを頑張ればいいかが見えてきます。転職前に「数字で評価される働き方」がどれだけ自分に合うか、少しでもイメージしておくことが、転職後のストレスを減らす助けになります。
ギャップ③:上司が若い人になること、そしてその関係づくり
公務員の教員時代は、上司=年上、先輩=年上という環境がほとんどでした。年齢が仕事の関係性の一部になっていたように思います。
でも転職後は、「年齢」はあくまで数字に過ぎず、役職や責任が重い人が若くても尊重される。年下の上司の指示を受けることもあります。最初は、「話し方」や「態度」に戸惑いがありました。
たとえば、会議で意見を言われたとき、「先生」としての論調で反論しそうになる自分。それでは場の雰囲気も悪くなるし、信頼を築く妨げになると感じました。そこで私は、相手の発言をまず受け止めて、「そうですね、その視点もわかります」と言うように心がけました。
仕事をともに進める中で、相手が若くても信頼を築けるようになり、今ではその関係性が自分の仕事をスムーズにしてくれています。年齢を気にするより、人としてどう関われるかを意識するようになりました。
ギャップ④:税金や手取りなど“お金の見え方”が変わる
教員のときも給与明細は見ていましたが、転職後、手取り額・税金・住民税・控除のことなど、お金の“見え方”がまるで違いました。
住民税は前年の所得で決まるため、転職直後の住民税で思わぬ大きな請求が来て、生活が一時的に苦しかったこともあります。特に子育て中は、なるべく貯金を多めにしておかないと、「月末までもたない…」という状況になることもありました。
また、ボーナスや昇給のタイミング、福利厚生なども、教員時代とは制度が異なっており、会社によってかなり差があります。転職前にこういった“会社側の制度詳細”をしっかり聞いたり、自分で調べることがとても大切です。
ギャップ⑤:“教員だった私”という思い込みを手放すことの大切さ
教員という仕事には誇りがあります。生徒を育てること、学校を支えること。そうした経験は私にとってかけがえのないものです。
でも転職後、私は自分の“教員としての肩書き”に甘えてしまった部分があり、それが思っていたほど役立たなかったことにも気づきました。「先生だからこうあるべき」という期待が自分を縛ることもありました。
そこで心がけたのは、「今の職場では新しい私でいよう」ということ。仕事のやり方や学び方が全く異なる環境なので、これまでの慣習をそのまま持ち込まないこと。自分が教員時代に培ってきたコミュニケーション力・企画力などを活かしつつ、会社で求められるスキルや価値観を柔軟に取り入れていくようにしました。
プライドを徐々に手放すのは勇気のいることですが、その過程で成長も見えてくるものです。
転職を乗り切るために私がしておいた準備

これらのギャップを乗り越えるために、私が転職前から少しずつ準備したことがあります。これは、これから同じ道を考えるあなたにもすぐに取り入れられることばかりです。
- 転職先企業の文化や雰囲気をリサーチする。社員の口コミや社長のメッセージなどを見て、「自分がそこで安心して働けるか」を想像すること。
- 転職活動と並行して、ビジネスマナー講座を1~2日受講しておく。敬語・電話応対・メールテンプレートなどを学んでおくと、最初の緊張がだいぶ和らぎます。
- 貯金のプランを早めに立てておく。住民税や初期の給料の差、保険料などを想定して、余裕を持った貯金を確保すること。
- 実際に働いている人に話を聞く。できれば一般企業で転職した元教員の体験。現場の声には教科書やネットにないリアルがある。
- 自分の強みと弱みを整理しておく。教員としての経験(指導力・企画力・クラス運営など)を「企業で活かせるスキル」として言葉にできるよう準備しておく。
転職してよかったと思える瞬間と、この先の可能性
転職後しばらくは、不安も戸惑いもたくさんありました。だけど少しずつ、良かったと思えることも増えてきています。
- 同僚や上司との距離感が自然になり、意見交換がしやすくなったこと
- 成果が数字として見えたとき、自分の仕事が形になっているという実感が持てるようになったこと
- プライベートの時間が少しずつ取れるようになり、子どもと夕食をゆっくり取れる日が増えたこと
- 会社の制度が合えば、福利厚生や休暇の使い方での柔軟さに助けられること
この経験を通じて、「教員時代から培ってきたもの」が無駄ではなかったと感じています。むしろあの働き方や経験があったからこそ、今の自分があるのだなと自信を持てるようになりました。
終わりに

もし今、教員として毎日を頑張っているけれど、「この先どうしよう」と悩んでいるなら。転職は簡単な決断ではないけれど、新しい可能性を開くものでもあります。
転職によるギャップをあらかじめ知っておくこと。自分が何を大切にしたいかを言葉にできること。それが、選んだ道で後悔しない大きな鍵になります。
この記事が、あなたの背中をそっと押すものになれば嬉しいです。あなたにふさわしい選択ができますように。
🌱 こちらの記事もぜひご覧ください。
👉 教員の経験を活かして在宅で働きたい!元教員におすすめの副業と転職先
👉 放課後等デイサービスの開業方法|元教員が法人設立から指定申請までをわかりやすく解説
👉〖子育て中の教員へ〗退職を現実にするための5つの準備